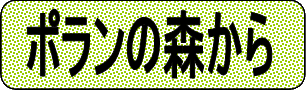ポラン便り 2020年度 第4号
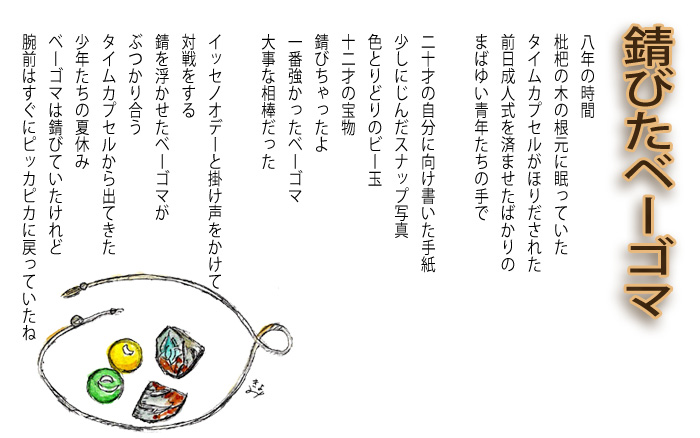
達成感を蓄積すること
正月の最初はいつも石巻登山から始める。落とし物として届けられた行き場のない10円玉や100円玉が竹筒に貯まっているので、一年分のそれを持って登り、神社に納めるのがいつの間にか恒例行事化している。今年は夏に《子供バザール》がなかったのでその金額は極端に少なかった。
最近は石巻山に登る人がめっきり減った。でも、大晦日から新年の三が日にかけてのこの時期だけは少し増えるようで、神社から山頂へ至る登山道は人の足で踏まれてやや荒れている。途中で自生するミカンを採るのが恒例だが、最近はその木に登りたいという子がいなくなった。今年も声をかけてみたが、ヒョロっと高くのびたミカンの木を見上げるばかりで誰も登ってくれる子はいない。落ちたりされても困るので、しかたなく、今年もジイサンが登ることにした。年寄りの手足の運びは年々、慎重になる。5mほどの樹上で呼吸を整えているボクのところに子供たちから「ロクさん、すご〜い」という声が届く。そんな言葉より、代わりに登ってくれる方がずっとうれしいのに、と思う。

山頂からは三ツ口池、地元の集落、ポランが見える。もちろん豊橋市街や豊川市街、三河湾や遠州灘など、ふるさとの風景が見渡せる。南アルプスの雪山やかすかに富士山の頭も見えた。記念撮影をして、さて、山頂から続くもう一つのピークまで行く希望者を募る。痩せた岩尾根づたいに数十メートル進んだ場所にそのピークはある。少しばかりスリルのあるコースだが、高い所が苦手でなければ、高学年なら行ける。今年は7人が名乗り出た。往復に時間がかかるので他の子は先に下山する。
そのピークは奥に見えてはいるのだが、ちょっと見ただけでは道があるのかないのか分からない。実際、あるのは一人ずつしか通れない狭い岩場を縫うような、道とは言えないようなものである。途中にはキレット(切戸)のように窪んだ場所もある。まずは、少し緊張感を持たせるために手足の運び方について話をする。そんなことにまで神経を使わないと進めない場所が実際にあるからだ。そして出発。最初の岩場を降りるところから気を抜けないコースであることを実感する。数メートル進むと最大の難所であるキレットに出る。手本を示しながら先に降りたボクが下から、手をかける場所、足を置く場所を指示する。降りたら次は隣の岩に体を伸ばして取り付き、その岩を抱えてカニの横ばいのようにして左に回り込む。一人ずつをそうやって進める。4人は越えたが、あとの3人はその様子を見てギブアップすると伝えてきた。ここは無理をさせるところではない。チョンが待つ元の山頂へ戻る安全な別ルートを教えて引き返させることにした。
この先にはそれほど緊張を強いる場所はない。人の背丈ほどの岩を登ったり降りたりしながら30メートルほど進む。そしていよいよ目的のピークに到着である。晴れやかな気持ちで周囲の景色を眺める。本来の山頂からは豊橋の街と金田の集落が見渡せるが、ここからは反対側の神郷の集落の全体が見渡せる。「来てよかった」。そんな言葉が聞こえた。

最初、「そこへ行くと何かいいことあるの」という声があった。よくある問いだが、この手の冒険的行為にはそれに対する明確な答えはない。しいて言えば達成感が得られることだろうが、それは裏を返せば自己満足でしかない。でも、その達成感には価値がある。勉学でも運動でもそして冒険でも、達成感や満足感や成功体験は、やがて《自己肯定感》のもとになり、《自信》となって子供たちの成長を支えることになる。オリンピックの表彰台を目指すアスリートが「そこに立った者にしか見えない景色を見たい」と口にすることがある。それは凡人には逆立ちしても見えない景色だろうが、石巻山の冒険コースでなら文字通り「そこに立った者だけに見える景色」を、逆立ちしなくても、ちょっと勇気を出せば見ることができる。そしてその景色を見た子の口から思わずこぼれた「来てよかった」という言葉は、実感のこもった達成感そのものだったように感じた。そしてそのときボクの頭をよぎったのは、PCゲームで得られる達成感と、こうして生身の全身を使って獲得した達成感とは、別物ではないかという思いだ。前者は簡単に揺らいだり消滅したりするが、後者は消えることなく蓄積され続けていくものだという気がする。体を動かすことが減ったこの時代、達成感すらもバーチャルな体験になり、本物の達成感を得るのが難しくなっているのかもしれない。
「おかえり」、新成人たち

カプセルから出てきたもの
今年成人を迎えた卒業生たち12人がポランに戻ってきてくれた。在籍中から、男女の仲がよく、まとまりのよい学年だった。進学や就職などで豊橋を離れている子も多く、東京はもちろん、富山、広島、北海道などで暮らしている者もいた。みんなが顔をそろえたところで、ビワの根元に埋めたタイムカプセルを掘り出すことになった。準備よく、埋めた場所の写真を用意していたが、6年の歳月の中で地表の様子が変わり、探し当てるのに案外てこずっていた。30分ほど地面と格闘した末に掘り出した容器の中からはベーゴマ、ビー玉、自分で削った竹箸、写真などが出てきた。竹箸は変色し、ベーゴマは少し錆びていた。ワー、キャー言いながら懐かしそうに手に取っていた。「二十歳になった自分へ」向けて書いた手紙も出てきて、時にケラケラと笑い、時に恥ずかしそうな表情を浮かべ、互いに見せあい、笑い合い、楽しそうだった。そんな姿を見ながら、この子らはポランで、イヤなこともいろいろあっただろうが、いい6年間を過ごしてくれたんだろうと思った。そしてその時間と空間を共有した者としても、静かな喜びと、そして職業柄だろうか安堵のようなものを感じていた。

ベーゴマに興じる青年たち
そんな時間が過ぎた後、ごく自然に始まったのがベーゴマだった。「アレ、巻き方、こうだったかなあ?」などと言いながらも、すぐに体が反応したようで、ベーゴマ台の周りにはいつの間にか昔と同じような輪ができていた。ベーゴマ、ビー玉、竹馬、元少・・・、子供時代に身につけたものは生涯忘れない。ベーゴマの後はダルマストーブの周りで談笑し、記念撮影をして解散となった。
この二十数年、ポランでは入学から卒業まで6年を過ごしてくれる子が多い。今年のように、成人や高校卒業などの節目に集まってくれる年もあれば、そうでない年もある。どんな学年も、どんな子も、いろんな遊びに夢中になり、充実した子供時代を送ってもらいたいというのがボクの42年?間、変わらない願いである。
部屋の中で焚き火
ダルマストーブが登場したのは年末劇が終わってから。それからほぼ毎日、火が入っている。今年は、換気のために窓を開けてあるので暖房効果は薄いが、デ〜ンと座る鉄の塊の存在感はそんなことに影響されはしない。周りに座る人数を制限しているが、ついつい大勢が集まってしまう。燃える火に人を引き付ける魅力があり、温かさを求める人間の本能がそうさせるのだろう。
火をつけようとしていると必ず誰かが、やりたい、つけさせて、と寄ってくる。マッチを擦って新聞紙に着火し、こっぱに移してだんだん火を大きくする。ストーブがまだ冷えているときは煙がでやすいので、薪を入れ過ぎないように注意する。その後ももちろん絶えず薪を補うわけだが、それも大好きだ。横開きの焚口の蓋(ふた)をパカパカと開いては薪を放り込む。蓋はなるべく閉めておいた方がいいのだが、開け放っていることが多い。燃え盛る炎を見たいのだ。そのために燃えやすい薄っぺらなものを入れたがる。ストーブの上に木片を置いて黒く焦げるのを喜ぶ。室内にこもる煙のことや煙突から出る火の粉のことを考えると、やってほしくないことがいろいろあるので、おおっぴらにやっている子には「寝しょんべんするゾ」と注意はするし、目に余る場合は、あえて必要以上の大げさな身振りで注意もする。でも正直にいうとココダケノハナシ、多少のことはユルシテヤリタイと思っている。焚き火には言葉にならない魅力がある。おそらく人間の動物的な脳(大脳の辺縁系)が関係しているのだろう。「遊びをせんとや生まれけむ」。平安時代からそんな風に形容される子供にとって、焚き火は暖をとるためというよりも遊びである。燃焼という物理的現象を体験するための遊びである。普段はあまりできなくなった焚き火という遊びの場が、毎日、しかも部屋の中にあるわけで、いじりたくなるのもやむをえないことだろう。

子供が火を扱う様子や、薪割り用の刃物が子供たちの周辺に放置してある光景を初めて目にする人の中には驚く人もいるようだが、そこは慣れである。日常の中で、火というものに慣れ、刃物というものの扱いに慣れていく。もちろん小さな火傷をしたり、指を切ったりする子はいる。その数はおそらくこちらが把握している倍以上になるのだろう。それは火であり刃物なのだからありうることだ。大人たちが実用のために刃物を使い火を使う。その傍で、子供は遊びながらその作業を目にし、慎重に取り扱う様子を学び、自分でマネをし、時々痛い目にあったりしながら、危険を伴うものの扱い方に慣れていく。そういう昔風の、ある意味で自然な暮らし方ができる場所がほとんど消えた今、ここの暮らしには何か価値が加わったと感じる。薪集めや定期的な煙突そうじなどの手間、耐用年数の少なさなど、デメリットはある。でも、ダルマストーブが放つやわらかな温かさと、捨てがたいイイ雰囲気、そして子供たちへの巧用を考えれば、メリットの方が大きい。火の元に十分注意しながら、いつまでも使い続けたいものだ。
150人の仲間づくり
少し前までは人と人の絆が尊重された。今、強調されるのはステイホーム、ソーシャルディスタンスで、人との接触は極力避けるべきものとされる。人のつながりが大切であることは変わらないはずなのに、ままならない。この先は、インターネットやオンラインを活用したこれまでとは違う人のつながり方やテレワークなど、新しい暮らし方を模索していくことになるのだろう。
ある生命科学者が指摘している。《生きものとして、お互いを十分理解し合いながら暮らしていける仲間は150人》だと。《生きものである》ことと《十分理解し合う》ことを考えると、なるほどと思う。WEBの中だと何千、何万の人とつながることができるが、生きものとしてのぬくもりを感じたり、理解し合える喜びが実感できるとは思えない。150人くらいならできそうな気がする。例えば小学校で考えると、1学年25人として6学年で全校児童150人。一人一人の顔と名前が浮かびそうだ。150人規模の会社や地域社会。大き過ぎず小さ過ぎず。この際、そんな規模の組織、集団づくりを目指すといいかもしれない。