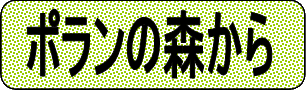ポラン便り 2025年度 第1号

スケボーが始まった。まず完成したのは初心者コース。一年生の中にはスケボー初体験の子がいる。まずは危険な目にあわないための注意をいくつか与えてから始める。傾斜がゆるやかな直線コースだからなのか、それとも子供たちのセンスがいいからなのか、どの子も上達がとても早くておどろいた。
対面で話すことについて
新しい年度がまだ始まったばかりだと思っていたら、ポランの水路の上をホタルが舞っている。天体望遠で星空をあかずに眺めていたのはついこの間だったと思うのに。ということはポランで次にきれいな光を見つめるのはキャンプファイアーと花火か。
さて、ボクは数年前から耳が聞こえにくくなった。老人性の難聴だ。耳の中、というより頭の中にセミの声のようなキーンという音が四六時中している。やや大げさに言うと、爆竹が耳元で爆ぜた時のような感じか。雑音のない場所なら会話にあまり支障はないが、雨の日のポランの室内は最悪だ。子供たちの声で騒然としている中で何か言われても聞き取れない。か細い女の子の声など特に聴き取りにくい。でも、ごく最近、あらためて気がついたことがある。それは相手の顔を見ながら話すことの意義。
きっかけがあった。我が家では普段は4人で食卓を囲む。ボクと妻は隣り合って座っている。他の家族がいない時にも横並びのまま食べながら話しをする。難聴になる前からの習慣でもあり、聞こえない時は聞き返すだけのことだった。ある時、何気なく妻の真正面に座ってお茶を飲みながら話し始めた瞬間、目に映る景色が変わった、ような気がした。ピントがシャキッとして色もはっきりとした、ように感じた。話の中身もよく伝わるような、気がした。横並びと何かが違う。ちょっと不思議な体験だった。
人と話すときは向かい合って顔を見ながら、というのが自然なことだ。言葉だけでなく互いの目や口元に浮かぶ微妙な表情、着ているものや周囲の状況なども大事な対話の要素だ。ただし、電話やネットなどのように言葉だけでも十分に意思は通じる。横並びでも作業をしながらでもスマホを見ながらでも、ほとんど不自由は感じない。でも、例えばボクのように、耳に何らかのトラブルが起こると、実際には「十分」ではないのかも、という思いが浮かんだのだ。対面とそうでない場合には意外と大きな差があるのかもしれない。子どもと話すときは目を見て話すことが大事だと、知識としては知っていた。コロナ禍の頃、マスクをした保育士のことが問題にされたのは、口元が見えないマスク保育で育つ乳幼児は将来、意思疎通に何らかの齟齬(そご)を来すのではないかという専門家の懸念が提起されたからだった。
授乳をする母親が赤子に注ぐ慈愛に満ちたまなざし、それに応えるかのようにウックンと喉を鳴らして微笑む幼な子。なんともほほ笑ましく、光やぬくもりさえ覚える光景だが、そこには人としての細やかな意思の疎通が始まる原点があるように思う。
春休み点描

三本松公園で遊ぶ。桜が満開。子供たちが真っ先に走って行くのは遊具。昔も今もそれは変わらない。

三ツ口池ひろば。リアカーで遊ぶ。帰る時にはタイヤが壊れていた。乱暴すぎるのか安物なのか。たぶん両方。

竹馬サッカー。激しくて痛い遊びだ。竹馬に乗って走り回り、蹴り進む。ボールを奪い合うときに硬い竹が頭や足にゴンゴンと当たる。相手の体より先に竹の棒が出て来るのだから当然だ。真冬でも5分で汗だくになる激しさと、痛さにめげていてはとてもできる遊びではない。

ウオークラリーの途中で訪れた浄水場。ふだん入れない場所を見られてラッキー

女の子たち(現2年生)が作ったフルーツセット?春の草花でできている。いつもながら女の子たちの観察力と創意工夫に感心する。

ブロックを積んで遊んでいた連中にシートを出してやったら突然プール遊びになった。バケツで水を何杯も運び、溜めて。ここでも子供たちの発想の楽しさに感心する。

綱引き。引き合うのは長い綱の他にも竹、輪っか、短いロープなどがある。自陣に引き込んだ数を競う綱引き。引きやすい物を先にねらう。力より作戦がものをいう。
春の合宿

テントを張った直後、とにかくまず中に入ってイエーイ。

翌朝の目玉焼き。卵を割り入れる。初めての子には緊張の瞬間だ。